24時間365日 受付中
- スマートフォンの場合、タップで電話がかかります。「ホームページを見た」とお伝えいただけるとスムーズにご案内できます。


病院から「危篤」の連絡を受けたとき、まず知りたいのは「あとどれくらい持つのか」と「今何をすべきか」です。私たち、法要館のお葬式は、松戸市の窓口情報を踏まえ、危篤の一般的な時間幅の目安、臨終直前に現れやすい具体的な兆候、医師へ短時間で確認すべき質問例、家族が優先する行動リスト、使える連絡文例までを実用的にまとめました。冷静に優先順位を決め、無駄なく動けるように設計しています。
危篤は医学的に「死期が近い可能性が高い状態」を指し、時間幅が非常に広い概念です。急性のトラブルで急変する場合もあれば、終末期の慢性疾患で数日〜数週間かけて徐々に進行する場合もあります。背景となる病気や現在の治療方針、延命の有無で見通しは大きく変わるため、医師の説明で「幅(例:24〜72時間)」が示される理由を必ず確認してください。
家族が受け取る情報は感情的に重く、混乱しやすいため、伝えられた言葉をそのままメモし、曖昧な点はその場で短く尋ね直しましょう。病院側は対応の幅を残すことが多く、具体的な治療名や現状のバイタルの傾向を素早く確認することで、今後の判断がしやすくなります。
危篤の時間軸はケースごとに差が大きいですが、現場でよく見られるパターンを知っておくと判断がしやすくなります。例えば、急性の大量出血や重度の心機能不全では数時間で急速に悪化することがある一方、終末期のがんや高齢による衰弱では1〜3日で臨終に至ることが多いとされます。重要なのは「個人差が大きい」点で、医師が示す幅(例:24〜72時間)を基準に行動してください。
また、小康状態を挟んで1週間以上持ちこたえる例や、短時間で急変する例もあるため、到着の遅れを最小化する準備(交通手段・連絡先の確保)と、到着後に確認すべき優先事項(延命方針・面会条件など)を整えておくことが実務上は有益です。
臨終が近づくといくつかの徴候が同時に出ることが多く、複数のサインが重なるほど臨終に近い可能性が高まります。代表的な兆候としては、呼吸の浅く不規則な変化(チェーンストークス様呼吸)、手足の冷感や紫がかった皮膚、尿量の著しい減少や失禁、意識レベルの低下と応答性の薄さなどがあります。これらは中枢や末梢循環の低下を反映しています。
また、聴覚が比較的最後まで残るケースが多いため、穏やかな声かけや好きだった音楽を小さく流すなどの対応は心のケアとして有効です。兆候が出た場合は医師や看護師に現状を確認し、必要なら鎮痛や苦痛緩和のための処置を相談してください。
限られた時間で確実に情報を得るために、質問テンプレを用意しておくと焦らずに済みます。短く具体的に聞くべき項目は、「今後24時間と72時間でどんな変化が予想されるか」「現在行っている延命処置は何か/今後どうするのか」「面会や夜間対応はどうなっているか」などです。質問は紙やスマホに箇条書きで持参して、聞き漏らしを防ぎましょう。
また、患者の事前指示書や本人の延命希望があれば提示し、医師と家族で方針の整合を取ることが重要です。緊急時は診療記録の要点(直近のバイタルや投薬、検査結果)を簡単に確認すると今後の判断に役立ちます。
混乱を避けるため、到着前に代表者を決めて情報を一元化することが最優先です。代表者は到着予定を病院へ連絡し、遠方の親族はビデオ通話でつなぐ手配を行ってください。また、病院へ到着予定時刻を伝えると面会調整が容易になります。事前準備が到着後の混乱を大きく減らします。
到着前に行うべき実務は明確です。代表者の決定、主治医へ「24〜72時間の見通し」と「延命方針」の確認、病院の面会ルールや駐車・宿泊可否の確認、必要書類や持ち物の準備を優先してください。これらをリスト化して連絡役が管理すると現場で迅速に動けます。
病院によって運用が異なるため、到着前に受付や病棟師長へ以下の主要項目を確認してください。特に重要なのは、延命処置の現状と今後の方針(具体的な処置名)、臓器提供の意思確認が必要かどうか、面会時間・人数制限・夜間対応の連絡先、搬送や安置に関する病院窓口の相談可否、身分証等の提示準備です。これらは到着してからの混乱を減らします。
面会時のマナーとしては短く穏やかな言葉かけを心がけ、長時間の滞在は交代で行うと周囲への配慮になります。病院側の指示に従い、他の患者や職員に迷惑とならないよう注意しましょう。必要な同意書類がある場合は速やかに対応できるよう準備しておくと安心です。
地域窓口を事前に把握しておくと臨終後の手続きや在宅引き取り、緩和ケアなどの相談がスムーズになります。松戸市では病院の相談窓口(例:東邦大学医療センター松戸病院の相談窓口等)や松戸市地域包括支援センターが在宅看取りや介護支援、緩和ケアの案内を行っています。事前にどこに相談するか把握しておくと安心です。
臨終後に必要になる代表的な手続きは、死亡届(通常7日以内)、火葬許可申請、国民健康保険の葬祭費申請などです。葬儀社を利用する場合は複数見積りを取り、夜間搬送の対応状況を確認してください。病院相談窓口で搬送や安置の手配が可能かを早めに相談するのが実務的です。
親族や職場へ伝える際は、伝えるべき要点を絞った短文を準備しておくと混乱を避けられます。親族向けは病院名・病室・代表者名・到着要否を明確に、職場向けは事実のみを伝え復帰予定は改めて連絡するといった形式が一般的です。短くても核心を伝えることで対応が早くなります。
心の準備としては、最期の時間に意味のある会話や静かな環境作りができるようにしましょう。聴覚が残る場合があるため、短い感謝の言葉や穏やかな音楽を用意しておくと良いです。また、家族同士で役割を分担し、感情的になりすぎないよう休憩を取りながら対応することをおすすめします。
個人差が大きく、一般的には数時間〜数週間という非常に幅のある状態です。急性疾患での急変なら数時間で展開することもあり、終末期の慢性疾患では1〜3日で臨終を迎えることが多いものの、途中で小康状態になる例もあります。
実務的には、医師に「今後24〜72時間の見通し」を具体的に示してもらい、その根拠(バイタルの傾向や治療反応)を聞いておくと到着の優先度や連絡すべき相手が決めやすくなります。
面会の人数制限や時間帯、夜間対応は病院ごとに規定が異なります。到着前に受付に電話して人数・時間・夜間対応の連絡先を確認し、複数名で来る場合は交代で短時間の面会をお願いする形が一般的です。
また、感染対策や病棟の事情で急に制限がかかることもあるため、到着したらまず窓口で最新のルールを確認し、看護師と簡潔に要望を伝えるとスムーズです。
延命処置については主治医に現在行っている処置名(人工呼吸、輸血、血圧昇圧薬など)と、今後その継続度合いを具体的に尋ねてください。患者の事前指示書や家族の希望があれば提示し、医師と方針を擦り合わせることが重要です。
可能であれば、処置中の目的(苦痛緩和か延命か)を明確にしてもらい、それに基づいて家族間で意思統一を図ると、臨終前後の判断がぶれにくくなります。
危篤は病状や治療方針により経過が大きく変わり、数時間〜数週間の幅があります。臨終直前には呼吸の乱れや末梢の冷感、尿量減少など複数の徴候が現れることが多く、これらを総合して判断します。まず代表者を決め、医師に24〜72時間の見通しと延命方針、面会の可否を確認し、身分証や薬リストを持参してください。松戸市の病院窓口や地域包括支援センターに相談し、用意した連絡文例で迅速に連絡を取り、短い言葉で感謝や静かな音楽を伝えることが心の支えになります。
まずお読みください
お気軽にご相談ください
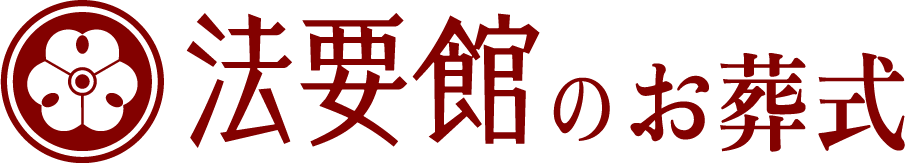
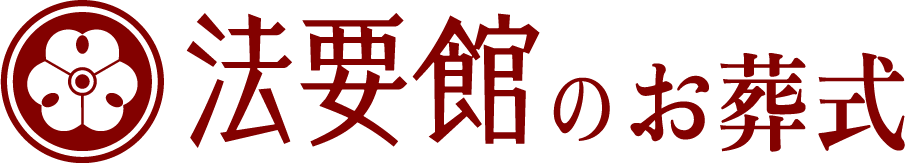
365日24時間受付中
お葬式の相談やご不明点など
お気軽にお問い合わせ下さい。
施行:株式会社セレモニー
株式会社セレモニーは、法要館の管理運営をする葬儀社です。
1979年に創業以来、病院、警察、介護施設、高齢者施設の搬送から葬儀までをサポートしています。